大阪市住吉区東粉浜の完全1対1個別指導塾、学友ハイスクールです。いよいよ寒さが堪える日も増えてきました。インフルエンザの流行も言われておりますので、みなさん体調管理には気をつけましょうね。
本日11月9日は、「行政書士試験」実施の日です。 「行政書士? 法律の資格でしょ? 高校生の私たちに何の関係が?」 そう思ったかもしれません。
確かに、皆さんが今すぐ行政書士試験を受けるわけではありません。しかし、大学受験を控える皆さんにとって、この試験から学べることは驚くほど多いのです。
なぜなら、行政書士試験のような難関国家資格は、「間違った努力」を続けた受験生が、最も報われない試験の典型だからです。そして、これは大学受験にも全く同じことが言えます。
今回は、行政書士試験を題材に、本番で「合格点」を掴み取るために不可欠な戦略的思考についてお話しします。
1. なぜ「真面目な人」が合格できないのか?
行政書士試験は、合格率わずか10%前後の難関試験です。憲法、民法、行政法、商法…と、高校の「政治・経済」や「現代社会」とは比べ物にならない膨大な範囲を学習します。
この試験で、最も不合格になりやすい典型的なパターンが、 「分厚いテキストを、1ページ目から100%完璧に理解しようとする人」 です。
一見、とても真面目で立派な姿勢に見えます。しかし、このアプローチは戦略的に「最悪」です。
- 時間切れになる:膨大な範囲を完璧にしようとすれば、試験日までに全範囲が終わるはずがありません。
- 全体像を見失う:細かな論点(=どうでもいい知識)にこだわりすぎ、合否を分ける「最重要分野」の演習がおろそかになります。
彼らの目的は、いつしか「合格すること」から「テキストを完璧にすること」にすり替わってしまっているのです。
2. その勉強法、大学受験でもやっていませんか?
この話、大学受験にそっくりだと思いませんか?
- 英単語:分厚い単語帳の「1番目から」覚え始め、後半は手つかずのまま入試本番を迎える。
- 数学:学校で配られた網羅系問題集の「A問題」ばかりを延々と解き、志望校で頻出の「C問題」に全く歯が立たない。
- 日本史:教科書の隅にある「文化史のマイナーな仏像」の暗記に時間を使い、合否を分ける「近現代の政治・経済史」がボロボロ。
これらはすべて、行政書士試験で不合格になる人と**同じ「戦略ミス」**を犯しています。
大学受験も行政書士試験も、満点を取る必要はありません。**合格最低点を1点でも超えれば「勝ち」なのです。 そのためには、「すべてを完璧にする」という幻想を捨て、「合格に必要な点数を、最短で確保するための戦略」**が不可欠です。
3. 「1対1」だからできる、個別の合格戦略
では、その「戦略」とは何でしょうか? それは、「やるべきこと」と「やらなくていいこと(捨てること)」を、志望校レベルに合わせて冷徹に仕分ける作業です。
しかし、この仕分け作業を高校生が一人で行うのは不可能です。 集団塾でも、「〇〇大学コース」という大雑把な分類しかできません。
これこそが、**学友ハイスクールの「完全1対1」**が真価を発揮する領域です。
私たちのプロ講師は、生徒との「対話」を通じて、まず現状を徹底的に分析します。
- 君の現状:基礎知識はどこまで定着しているか? ケアレスミスが多いタイプか?
- 志望校の要求:過去問の傾向は? 必要な知識の「深さ」と「広さ」はどれくらいか?
この両者を突き合わせ、**「今の君が、〇〇大学に合格するために、今週何をすべきか」**というレベルまで、学習計画をミリ単位で最適化します。
「この問題集は、今はやらなくていい」 「この分野は、基礎のA問題だけでいい。その代わり、この分野は応用まで完璧にしよう」
この**「個別の戦略的取捨選択」**こそ、膨大な試験範囲から合格点を掴み取る、唯一無二の方法なのです。
まとめ
難関試験である行政書士試験も、大学受験も、本質は同じです。 「何をやるか」ではなく、「何をやらないか」を決める勇気と戦略が合否を分けます。
学友ハイスクールは、単なる「勉強を教える塾」ではありません。 君だけの「合格戦略」を立案し、実行を伴走する「戦略的パートナー」です。
「努力しているのに、成績が伸びない」 そう悩んでいる君は、その努力の「方向性」が間違っているのかもしれません。 学友ハイスクールで、無駄の少ない最短距離の学習で頑張っていきましょう!


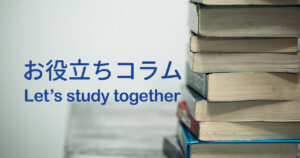
コメント