大阪市住吉区東粉浜の完全1対1個別指導塾、学友ハイスクールです。明日は敬老の日で学校もお休み、みなさんリラックスしてお過ごしでしょうか。
9月の連休、どのように過ごすか計画は立てていますか?その中には「敬老の日」がありますね。「おじいちゃん、おばあちゃんの家に遊びに行く」「プレゼントを渡す」など、身近な人を思い浮かべる日だと思います。
その温かい気持ちはもちろん、とても大切です。でも今年は、もう少しだけ視野を広げてみませんか? 実は「敬老の日」は、君たち自身の未来と、日本という国がこれからどうなっていくのかを考える、絶好の機会でもあるのです。
そもそも「超高齢社会」って何だろう?
ニュースや現代社会の授業で「超高齢社会」という言葉を聞いたことがありますよね。これは、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が21%を超えた社会のこと。そして、日本は世界で最もその割合が高い国の一つで、現在では約29%、つまり国民の3〜4人に1人が高齢者という時代に突入しています。
なぜこうなったかというと、理由はシンプルです。
- 平均寿命が延び、長生きする人が増えた(長寿化)
- 生まれてくる子どもの数が減った(少子化)
この「超高齢社会」、君たちが社会の中心となる10年後、20年後には、さらに進んでいると言われています。これは、遠い未来の他人事ではなく、君たちが真正面から向き合うことになる社会の姿なのです。
どんな課題があるの?私たちに関係ある?
では、超高齢社会が進むと、具体的にどのような課題が出てくるのでしょうか。いくつか例を見てみましょう。
- 社会保障の問題:年金や医療、介護といった社会保障は、主に現役世代(働く世代)が納める保険料で支えられています。高齢者が増え、現役世代が減ると、一人ひとりの負担が重くなる可能性があります。
- 働き手不足:社会を動かすためには、様々な分野で働く人が必要です。医療や介護の現場はもちろん、建設、運輸、サービス業など、多くの業界で人手不足が深刻化するかもしれません。
- 社会インフラの維持:道路や水道、公共施設など、今当たり前に使っているものを維持管理していくためにも、人手やお金が必要です。これらが将来も同じように維持できるかは、大きな課題です。
これらの課題は、君たちが大学を選び、職業を決め、家庭を築いていく、まさにその人生のステージに直接関わってくることなのです。
未来の主役である、私たち高校生にできること
「なんだか大変そうな未来だな…」と不安に思った人もいるかもしれません。でも、心配しないでください。未来は創っていくものです。課題があるということは、そこに新しい発想や活躍のチャンスがあるということです。
では、今、高校生である私たちに何ができるでしょうか?
1. まずは「知ること」から始めよう
まずは関心を持つことが第一歩。敬老の日をきっかけに、おじいちゃんやおばあちゃんが若い頃の話や、今の生活で感じていることを聞いてみましょう。教科書だけでは学べない、リアルな社会の姿が見えてくるはずです。新聞やニュースで関連の特集を読んでみるのもいいですね。
2. 世代を超えて「交流すること」
地域のボランティア活動に参加したり、近所のお年寄りと挨拶を交わしたり。異なる世代の人と話すことで、新しい発見や学びがたくさんあります。多様な価値観に触れる経験は、コミュニケーション能力を養い、人間的な深みを与えてくれます。
3. 「自分の未来のキャリア」と結びつけて考える
ここが一番大切なポイントです。社会が抱える課題は、君たちの将来の活躍の舞台でもあります。
- 工学・情報学に興味があるなら… 高齢者の生活を助ける介護ロボットや、遠隔医療システムを開発できないだろうか?
- 医学・看護学に興味があるなら… 健康寿命を延ばすための予防医学や、新しい地域包括ケアの形を創れないだろうか?
- 経済学・経営学に興味があるなら… シニア層向けの新しいビジネスや、年齢に関わらず誰もが活躍できる社会の仕組みをデザインできないだろうか?
- 建築学・都市デザインに興味があるなら… 誰もが安全で快適に暮らせるユニバーサルデザインの街づくりを提案できないだろうか?
このように、社会課題と自分の興味・関心を結びつけると、「何のために勉強するのか」という目的が、より明確になります。志望校や学部を選ぶ上でも、大きなヒントになるはずです。
まとめ
今年の敬老の日は、大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに感謝を伝えるとともに、ぜひ「私たちの社会と未来」という大きなテーマにも思いを馳せてみてください。
学友ハイスクールでは、学習を通じて得られる知識や思考力は、すべて未来の社会をより良くするための力になると考え、指導するよう心がけています。皆さんが社会の課題を乗り越え、未来を切り拓く主役となれるよう、全力でサポートしていきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう!


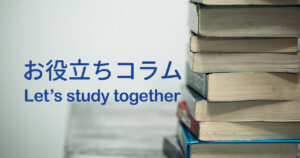
コメント