大阪市住吉区東粉浜の完全1対1個別指導塾、学友ハイスクールです。秋も深まり、いよいよ中学入試の本番が近づいてきました。
各中学校でも、プレテスト(模擬試験)の結果が返却され、ご家庭でも様々なドラマがあったかと思います。
「A判定が出てホッとした…」 「C判定で、あと一歩届かない…」 「E判定で、親子で落ち込んでしまった…」
毎年、この時期のプレテストの結果を見て、私たちは塾生に同じことを伝えています。 それは、**「A判定でも油断してはいけないし、E判定でも全く悲観する必要はない」**ということです。
なぜなら、この時期の模試の「判定」そのものには、ほとんど意味がありません。 重要なのは、その判定が出た**「原因」を徹底的に分析し、入試本番までの残り数ヶ月の「戦略」**に落とし込むことです。
今回は、プレテストの結果を「本番での合格」に繋げるための、プロの分析方法をお伝えします。
1. 最初に捨てるべきもの:「判定」と「偏差値」
まず、結果が返ってきたら、一番大きく書かれている「志望校判定(A〜E)」と「総合偏差値」は、いったん無視してください。
- 判定を気にすべきでない理由
- プレテストは、あくまで**「現時点での立ち位置」**を示すものであり、「未来の合格可能性」を予言するものではありません。A判定で油断して失速する受験生、E判定から戦略的に逆転する受験生を、私たちは毎年見ています。
- 偏差値を気にすべきでない理由
- 総合偏差値は、得意科目と不得意科目が平均化された「ぼんやりした数字」です。志望校合格に必要なのは、総合点ではなく、**「各科目の合格者最低点を超えること」**です。
2. 分析すべきは「3つの失点」
本当に見るべきは、「成績推移」でも「志望者順位」でもありません。 **「解けなかった問題」**です。
お子様が失点した問題(×がついた問題)を、以下の3種類に分類してください。
- ① ケアレスミス(知っていたのに間違えた問題)
- 計算ミス、漢字の書き間違い、問題文の読み飛ばし、単位の付け忘れなど。
- ② 知識不足(あと一歩で解けた問題)
- 塾で習ったはずだが、ド忘れしていた公式。暗記があやふやだった歴史の年号など。
- ③ 完全な実力不足(手も足も出なかった問題)
- そもそも解き方の方針が立たない、見たこともない応用問題など。
3. 「失点の種類別」本番までの処方箋
分類できたら、それぞれ対策の優先順位が変わります。
【最優先】① ケアレスミスの撲滅 これが一番重症です。なぜなら、入試本番で合否を分けるのは、この「本来取れるはずだった5点、10点」だからです。 「ケアレスミスノート」を作成し、**「なぜ間違えたのか(例:急いでいたから)」「どうすれば防げたのか(例:計算スペースを広く取る)」**を自分の言葉で書かせ、本番直前まで見直させてください。
【第二優先】② 知識不足の穴埋め これは「伸びしろ」の宝庫です。塾のテキストやノートに戻り、「なぜ忘れたのか」を確認します。単なる丸暗記になっていませんか? **本番までにやるべきことは「新しい問題集」ではなく、「今まで使ったテキストの完璧な復習」**です。穴の空いたバケツ(=あやふやな知識)に新しい水(=応用問題)を入れても意味がありません。
【後回し】③ 実力不足の問題(いわゆる「捨て問」) 驚くかもしれませんが、これらの問題は**「今すぐ解けるようになる必要はありません」。 特に難関校志望の場合、合格者平均点と満点には大きな差があります。つまり、合格者でさえ解けない「捨て問」が必ず含まれています。 プレテストでこのレベルの問題に時間を使いすぎて、①や②の問題を落とすことこそが「不合格」への最短ルートです。まずは、「全員が正解する問題を、絶対に落とさない」**訓練を優先してください。
学友ハイスクールの完全1対1指導では、プレテストの結果を講師が徹底的に分析します。
- 生徒一人ひとりの「失点のクセ」を特定し、ケアレスミス防止の具体策を指導します。
- 志望校の傾向から、「今やるべき問題」と「今は捨ててよい問題」を明確に仕分けし、本番までの最短カリキュラムを再構築します。
テストの結果に一喜一憂している時間はありません。 重要なのは、その結果を使って「次の一手」をロジカルに決めることです。
プレテストは、本番で合格するための最高の「予行演習」です。 その価値を最大化するために、ぜひ今日の分析法を試してみてください。学友ハイスクールで、合格に向けて一緒に頑張っていきましょう!


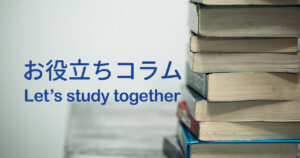

コメント